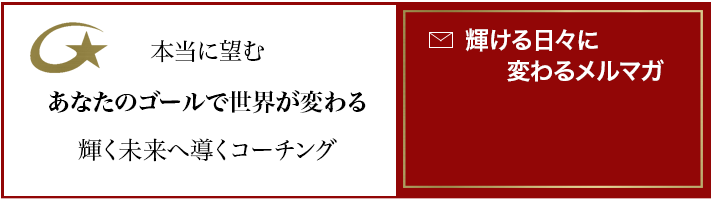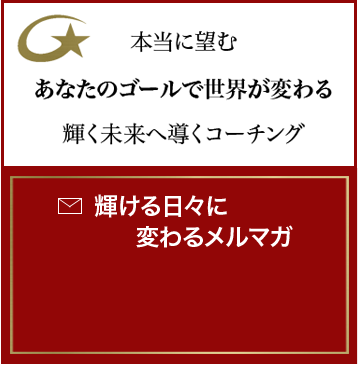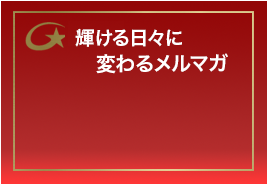こんにちは!コーチ敬人です。
私の活動の、少なくとも20%は音楽活動。
というわけで、今日は、音楽の話を。
音楽メディアは、この50年で様変わりしました。
私が生まれる前は、LPレコード。
自分で音楽を選んで聴くようになった頃にCDが出て、
今や、MP3。
しかし
音源はというと、
それほど変わらない。
やはり中心は、人間の声、つまり歌。
たとえ同じ曲であっても
アレンジのしかたや
声の出し方
その他もろもろで
まったく異なる世界が浮かび上がってきます。
これは、楽器でもいっしょ。
同じ楽器なのに、弾く人が変わると、まるで違う世界がそこに生まれます。
ところで
現在、世界的に一番メジャーな楽器はなんでしょうか。
統計的にみると
1位 ピアノ
2位 ギター
3位 バイオリン
となるようです。
確かに
日本人であれば、ピアノを触ったことがないという人は、ほぼいないでしょう。
学校に必ず一台はありますし
昨今、駅にピアノが置いてあったりします。
習い事の上位にも、ピアノは登場します(最近は電子ピアノが主流のようですがピアノはピアノです)。
これが、ギターとなると・・・ バイオリンとなると・・・
確かに、絞られてきますね。
なにより、ピアノのいいところは
誰が弾いても、指一本でドの鍵盤をたたけばドがでます。しかも、ドレミファソラシド・・・ときれいに順番に並んでいます。
これがギターとなると、押さえ方が意外と難しいですし、
バイオリンにいたっては、フレットもないので、同じ音を出すのすら難しい。
そのあたりが、鍵盤楽器たるピアノの優れた、メジャーたる所以でしょう。
ところが
ピアノは奥が深い。
たたき方により、音程も変わる不思議な楽器なのです。
そもそも、ピアノの先祖であるクラヴィコードは、叩き方により、音程が変わるどころかビブラートもかけることができます。弦をたたく、という基本は今のピアノと同じですから、上手にやれば当然、ピアノも音程を変えることができます。(とはいえ電子ピアノは無理。この場合のピアノといえばグランドピアノを指します)。
しかし
多くのピアノ弾きの人は、この事実をあまり重視していません。
ピアノを生業にしようとしている音楽大学の生徒に聞いてみるといいでしょう。
「ピアノって弾き方で音程かわるんですよね?」と。
たいていは、
「ドの鍵盤をたたけば同じドの音がでます。もちろん調律すれば音は変わるけど」
といわれるでしょう。
しかし、それは事実ではありません。
私が学生時代、合唱の練習でピアノの伴奏の譜めくりをしていたとき、今は亡き指揮者の汐澤安彦先生が、
合唱でなくピアノ弾きに対して「音程が悪い」といって、みんなの前でつかまえていたのが忘れられません。
実は、このときまで、私はピアノも弾き方で音程を変えられることを認識していませんでした。
この時は、ピアニストも言われた意味がわからず、「調律が・・・」と言いわけしていましたが、全く許してもらえず、何度も弾き直しさせられていました。もう、見るからに冷や汗をかきながらみんなの前で頭を抱えながら弾いていましたが、なんと、いわんとすることを理解し、先生からOKを出されました。(そのあと、ピアニストと居酒屋にいき、ことの顛末を二人で興奮して語り合ったのが忘れられません)。
それ以来、私は、ピアニストに対し、音程のいい人、音程を気にする人、というのを意識するようになったのですが
実は、そんなピアニストは何人もいません!
聞き手側もそこまで聞いている人は、そう多くありません。
しかし
生演奏を聞けば、だれでも感じているのです。
「キラキラと輝くように美しい」とか「しっとりとしている」とかいう感覚で。
特に、さまざまな調を、ひとつのコンサートで弾くと、その様がよくわかります。
(調というは、ハ長調とか、ニ長調とかいう、調です)
作曲家というのは、それぞれの調ごとに雰囲気、色合い、感覚、世界観をもっています。
なので、特にクラシック音楽においては
「モーツアルト作曲交響曲第41番ハ長調」とか「ブラームス作曲ヴァイオリン協奏曲ニ長調」といったように曲名にかならず調名が記載されていています。
ギター曲でも「Cmajorで」とか「Dmajorで」とかいうコードは重要ですね。
よくいわれるのが、
ハ長調は、
純粋・明るい・素朴・力強いが過度に感情的ではない・客観的でニュートラル・天真爛漫・自然体
ビートルズの「レット・イット・ビー」はその代表ですね。「ヘイ・ジュード」も出だしはハ長調です。
ニ長調は、
明るく澄んだ輝き・力強い前向きさ・開放感・のびやかさ・威厳・勝利感
ビートルズでいうと、ヘイ・ジュードが途中で転調してニ長調になります。高らかに、ラ・ラ・ラ〜となるところ。
楽曲に、調はとても重要なのですが、それというのも、音と音の感覚は等間隔でなく、曲調により、あるいは弾き手により間隔が広かったり狭かったりするからです。
特にクラシック音楽のピアノ曲でいうと、
バッハ、ショパン、チャイコフスキーが、各調の雰囲気をまとめた曲をだしています。
まるで「私の調性音を<絵の具の色見本(パレット)>に例えるならはこれだ!」と言わんばかりに。
ちなみに、
バッハ「平均律クラヴィーア曲集」は12の長調、12の短調、しかも2巻にわたります。つまり、24調 × 2巻 = 48の前奏曲と48のフーガという内容です。
ショパン「24のプレリュード」も12の長調、12の短調を扱っていますが、バッハと違い、循環五度(Circle of Fifths)の順番で曲が並んでいます。
チャイコフスキー「四季」は、網羅的に調を並べていませんが、季節ごとに、12の調を選び出しています。
というわけで、
これらの曲を一気にコンサートで取り上げるピアニストは、当然、調に敏感で、弾き分ける自信がある、というか、そこを聴かせたいという目的があるピアニストなのです。その力量が試されるわけで、ピアニスト多しといえども、そうそういません。
逆にいえば、この3曲をいろいろなピアニストで聴くと、その解釈の違いがとてもおもしろい。
とはいえ、繰り返しになりますが、この3曲でレコードを出したり、全曲コンサートをやる人は、そうそういないのです。
その、私が知る数少ないピアニストの一人が、松田華音さんです。
12月1日に、東京・オペラシティーで、まさにチャイコフスキー「四季」を演奏します。
https://www.japanarts.co.jp/concert/p2176/
せっかくですので、CDで予習をして聴かれると、天性脳覚醒ともいうべき脳体験が得られるかもしれません。
(CDと生演奏の違いも体験できるでしょう)
さらに、苫米地博士の著書
『音楽と洗脳』
をあわせて読むと、言うことなしです。
輝ける未来を、コンサート中に体験することとなるでしょう。
もちろん、私もいきます。
おしゃれをして、コンサートホールで、そのすばらしい演奏を聴くだけでも幸せですが、
コンサートの休憩時間あるいは終了後、知り合いを見つけて、感想を述べ、共有することでさらに至福は高まります。
私をみかけたら、ぜひ、声をかけてください。
2025年11月6日 23時30分